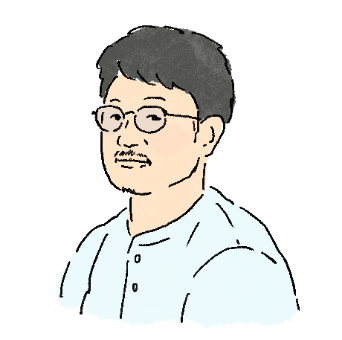また一人の患者さんのお看取りをさせていただいた。
医師になって11年、在宅医になって5年、多くの看取りに立ち会わせていただいた。
中には、ご家族が大パニックになり壮絶な最期になったこともあるが、多くはしめやかな雰囲気の中で粛々と医師としての責務を果たしてきた。決して形式的な儀式にならないよう、ご家族の気持ちの揺らぎを感じながら、可能な限り時間をかけることを心掛けていた。決して心地よいと思える時間ではないが、ご本人の生きてきた証としての“死にざま”を、そしてご家族が大切な家族を失った悲しみ中でこれからを歩んでいこうとする“生きざま”を見届けてきた。
その中で今回のお看取りで、初めて「いつまでもこの場にいたい」と思える経験をした。
この患者さんは、末期がんで余命1~2週と入院先で告知され、残りの時間を自宅で過ごすことを選択された。退院直後は全身の痛み、呼吸困難感などが強く、訴えを聴きながら薬の調整を行い、徐々に笑顔で冗談が言えるほどに身体症状は緩和された。しかし、寝たきりで動けないことによるつらさ、同じ部屋で何もせずに過ごすつらさ、眠ると二度と起きられないのではないかという不安、死への恐怖が本人を苦しめるようになった。会うごとに「死んでもいい?」という言葉が聞かれ、それが睡眠不足の中必死で付き添うご家族を苦しめた。こんな時に医学ができることは限られている。不安を鎮めるような安定剤を飲んでもらうことも一つの選択肢だが、これまでの経験上、それは気休めにもならないことを知っていたし、今となっては「逃げの一手」と私自身は思っている。というか、当時の自分はそれ以外の対応方法を持ち合わせていなかった。自分の弱さと徹底的に向き合ったことで、逃げたくなった時ほど、自分の理念に立ち返るようになった。
「自分はどんな医療をしたいのか?」
在宅医療の先輩医師から言われた一言が頭の中で浮かぶ。
「解決できなくても、我々医師は向き合うしかないんだよ。」
覚悟を決め、ひたすら向き合った。それで何かが劇的に変わるわけではないこともわかっている。でも、かすかな希望と圧倒的な絶望の中でゆらぐ患者さんの心の傍に、ただただ一緒にいた。
その時間をともにする中で、「リビングのベッドの上でただじっとしているのがつらい」と患者さんが言ったので、「もし動けるとしたら何かしたいことがありますか?」と尋ねると、「ガレージにある車を磨きたい」と言った。元々旧車が好きで、ガレージにはピカピカに磨き上げられた旧車が2台並んでいる。
元気な時は、一日のほとんどの時間をガレージで過ごしていたという。
「やりましょう!」と伝え、あっけにとられる本人をよそ目に、すぐに動いた。
関係職種にサポートを依頼。移動方法、リスク回避策、人手の確保などみんなで知恵を出し合い、中には在宅チーム外から利益度外視で協力を買って出てくれる方もいた。みんなが一つになっていた。すべての準備が整い、ご本人に日程を伝えると、「想像しただけで泣けてくる」と嬉しそうに涙された。
その2日後、病状は一変した。
ご本人の表情が曇り、普段は言う冗談も言わず、「死にたい」の言葉が出る。眠ることへの恐怖のため、極度の睡眠不足が続いていたため、一度しっかり眠ることを提案すると本人も同意したため、薬で眠ってもらった。その日から明らかに尿量が低下し、夜間は初めて覚醒することなく眠ることができたが、翌日昼になっても傾眠は続いていた。やはり尿量が少ないままだった。ご本人の希望を叶えるのは3日後に迫っていたが、そこまで間に合うかは微妙だった。間に合ったとしても、本人が眠ったままでは意味がない。何としても大好きな車を眺めてほしい。今日しかない。
予定を変更し、再度調整。全員がそれぞれでできる調整をして、その日のうちに決行することになった。当初の予定では、リビングから布担架でストレッチャーまで本人を移乗し、自宅となりのガレージに移動する予定だったが、わずかな体動でも呼吸困難感が出るため、介護ベッドを大人6人で持ち上げて窓際まで動かし、窓際から駐車場に移動した2台の旧車を眺めてもらう作戦にした。
その日のためにご本人の40年来の旧車仲間が駆けつけてくれて、息子さんとともに2台の旧車にエンジンをかける。
ブウォーン!!
けたたましい二つのエンジン音が鳴り響くと、それまで閉じられていた本人の目がぱっと開き、2台の愛車を眺めながら、旧友との再会に涙し、ご家族を見ながら「ありがとう…」。
その言葉に、娘さんが「お父さん、よかったね、嬉しいね…」と涙され、その場にいるすべての人がその光景に身を委ねていた。
その半日後に息を引き取られた。
死前期喘鳴が出現した時点で、鎮静剤を投与、眠るような最期だった。呼吸停止後もあまりに穏やかにうっすら微笑んでいるような穏やかなお顔だったため、娘さんから「お父さん、起きてもいいよ」などと笑いながら言葉が出たほどだった。
死亡診断書をご家族にお渡しし、通常なら医師としての責務はこれで終わり、その場をあとにしてもいいのだが、なぜだか“まだこの場にいたい”と思えた。
息子さん、娘さんがエンゼルケアを手伝う間も、「お父さんこの服好きだったよね。やっぱりイケメンだ!」とご本人の思い出話で和やかな空気が流れていた。
一言で、穏やかに自宅で最期を迎えるとは言っても、それはたくさんの奇跡の積み重ねの結果なのだ。
自宅に帰りたくても、家族がいなければ、そしてその家族が覚悟を持てなければ帰ることはできない。
それをクリアして自宅に帰ってきても、家族をはじめとした関係者全員の思いが同じ方向を向いていなければ病院に逆戻りすることもある。最後まで自宅で頑張ってこられた家族が、看取りの時になって耐えきれず救急車を呼ぶこともある。在宅医駆け出しの頃は、こういったご家族の変化に自分がついていけず、やきもきしたり腹を立てたりしたこともあった。
最近ようやく気付いた。人間、大切な人がいなくなる状況下で、こころがゆらがないわけがない。
そのゆらぎに、在宅医としてどう向き合えるか。
大事なのは「どこで過ごすか」ではなく、「誰とどう過ごすか」だということが、ようやく腑に落ちた。
今回の患者さんは、本人も家族も最期は自宅で過ごすことを希望され、幾多のハードルを乗り越えて、家族みんなが笑顔で記念撮影ができるような最期を迎えることができた。
そしてご自宅を出る際に娘さんから、「私、この2週間楽しかったです。」という言葉をいただいた時に、これまで味わったことのない感覚に陥った。
確かに家族の希望通り自宅に帰り、ご本人の願いも叶えることができた。とはいえ、その間強くてかっこいいお父さんの死の恐怖に震える姿や、抱えきれない不安を怒りで家族に表出する姿もみているはず。そして、最愛のお父さんが志半ばにして亡くなったのである。娘さんの結婚式にも出席できず、孫を抱っこすることもできていない。後悔がないわけがない。にもかかわらず、「楽しかった」という言葉が出たのだ。これは一重に、娘さんの人柄であり、その心をはぐくんだご本人と奥様の力である。
そして、この一連の奇跡を紡ぎだした在宅チームの思いが一つになった結果である。
「自分はどんな医療がしたいのか?」に対する答えは、「こんな医療」である。
この先どんな状況になったとしても「こんな医療」を続けていくために、うちのチームは対話と内省を積み重ねて強くなっていく覚悟を再認識することができた。